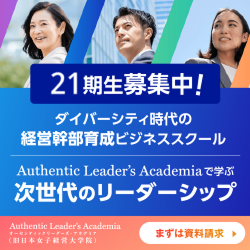総研コラムでは、わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)(WMSC)の研究員らが「企業で働く個人のユニークネスと組織のオリジナリティを最大限に発揮する」ためのヒントとなるような知見や情報を提供します。コロナ禍による行動制限の影響は文化芸術にも及び、「文化芸術は不要不急なのか」といった論争が起きたことも記憶に新しいかと思います。
本記事では、「文化芸術」と「ウェルビーイング」、この2つの関わりについての研究についてご紹介します。
執筆者:アイデンティティー・パートナーズ株式会社 わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所) 研究員/データサイエンティスト 風早 伸彦
【 目 次 】
深刻化する労働者のメンタルヘルス

2024年10月現在、世界各地では戦争が繰り広げられ、不安定な情勢が続いています。
日本国内に目を向けると、今年は大地震に始まり、夏の酷暑や台風・豪雨といった深刻な自然災害が相次いで発生しています。
数年間続いたコロナ禍による行動制限はほぼなくなったものの、コロナ禍を経て、「ニューノーマル」「新しい生活様式」に人々の生活が変化(揺り戻しも起こっていますが)する中で、リラックスやリフレッシュといったメンタルヘルスの健康、ウェルビーイングの向上が重要視されるようになってきました。
現実問題として、近年、日本では労働者の 82.7%が「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスと感じる事項がある」というデータもあり、健康やメンタルヘルスに関するさまざまな社会課題が深刻化しています(令和5年 労働安全衛生調査 より)。

博物館の持つ癒しやリフレッシュ効果とは?「博物館浴」の研究から見える文化芸術とウェルビーイングの関わり

「文化芸術」と「ウェルビーイング」の関わりについて、興味深い研究がありました。
九州産業大学地域共創学部地域づくり学科、緒方泉特任教授が進めている「博物館浴」の研究(実証実験)です。
「博物館浴」とは、博物館の見学を通して、博物館の持つ癒し効果を人々の健康増進・疾病予防に活用する活動を指します。
研究の詳細は次の記事をご覧ください。
九州産業大学 地域共創学部「国立西洋美術館で博物館浴実証実験を行いました」
要諦…
・博物館の持つ癒しやリフレッシュ効果を血圧や心理測定で数値化、健康促進や疾病予防に活用する「博物館浴」の研究(実証実験)を2019年から進めている
・被験者データは累計で1,000人超となった
・上の記事では、2024年6月24日(月)と7月8日(月)に、国立西洋美術館(東京都)で「博物館浴」の実証実験を行った
・「大学生」「会社員」「育休復帰者(女性)」「高齢者」を対象に、展示鑑賞とその前後の生理測定および心理測定を行い、リフレッシュ効果を科学的に分析した
・館内の2つの展示室に分かれ、それぞれ同じ展示室で2回鑑賞を行った
・1回目は一人で作品を観る「黙々鑑賞」、2回目はグループを組み、お互い気に入った作品の紹介や感想を共有しながら観る「おしゃべり鑑賞」を実施
・鑑賞前、1回目の鑑賞後、2回目の鑑賞後、の3回で生理・心理測定を実施し、作品や展示空間、鑑賞方法の違いでリフレッシュ効果にどのような影響が生じるのか検証を行った
・今回の実証実験の結果は考察中の段階
・過去の実証実験でも、鑑賞によって、ネガティブな気分状態が低減、血圧・脈拍(生理測定)は下降、心理ストレスの低減に影響を与えていることが検証されている
心身の健康に寄与する文化芸術は、社会に欠かせない存在

上の記事では、国立西洋美術館で行われた「博物館浴」の実証実験を紹介しています。文化芸術の鑑賞が心身に与える効果を測定し、癒しやメンタルヘルス改善につながることを科学的に検証する取り組みです。
私は趣味で音楽を楽しんでおりますが、文化芸術は社会に欠かせない存在だと感じています。文化芸術に触れることで、心が豊かになり、教養も深まると考えます。
この記事は、文化芸術が単なる「娯楽」にとどまらず、心身の健康に寄与する点で非常に意義深いと感じました。社会において文化芸術をより積極的に活用し、心のケアや教育に取り入れるべきだと再認識させられます。このような実験が、文化芸術の持つさらなる可能性を示している点に感銘を受けました。
また、一人での鑑賞だけでなく、グループでの「おしゃべり鑑賞」を行ったことも興味深いです。
当研究所「わたし・みらい・創造センター」では、人と人の対話によってイノベーションがどのように促進されるかを研究しておりますが、グループでの対話、つまりは作品から受けた印象を言語化し、その感想をお互いにシェアしたことで、鑑賞者は新たな発見(イノベーション)を得たのではないかと思います。
そのイノベーションのために何が寄与していたのか、今後の我々の研究にも大いに関わってくることだろう、と感じました。
WMSCのセミナー・イベント情報はこちら
▼この記事を書いた人
風早 伸彦(かざはや のぶひこ)
〈プロフィール〉
慶應義塾大学で統計学を専攻、2016年にSBIビジネスサポート(現SBIビジネス・イノベーター)へ入社。教育研修部門でのアンケート分析、コールセンター部門でのAIを活用した時系列予測、BIツールを使ったデータ可視化に取り組む。2018-2020年でSBIホールディングスへ出向、ビッグデータ解析に従事。当社では、研究員としてAIによる対話能力の可視化や統計解析に従事。2017年に統計検定2級、2022年にデータサイエンティスト検定リテラシーレベルの資格を取得。